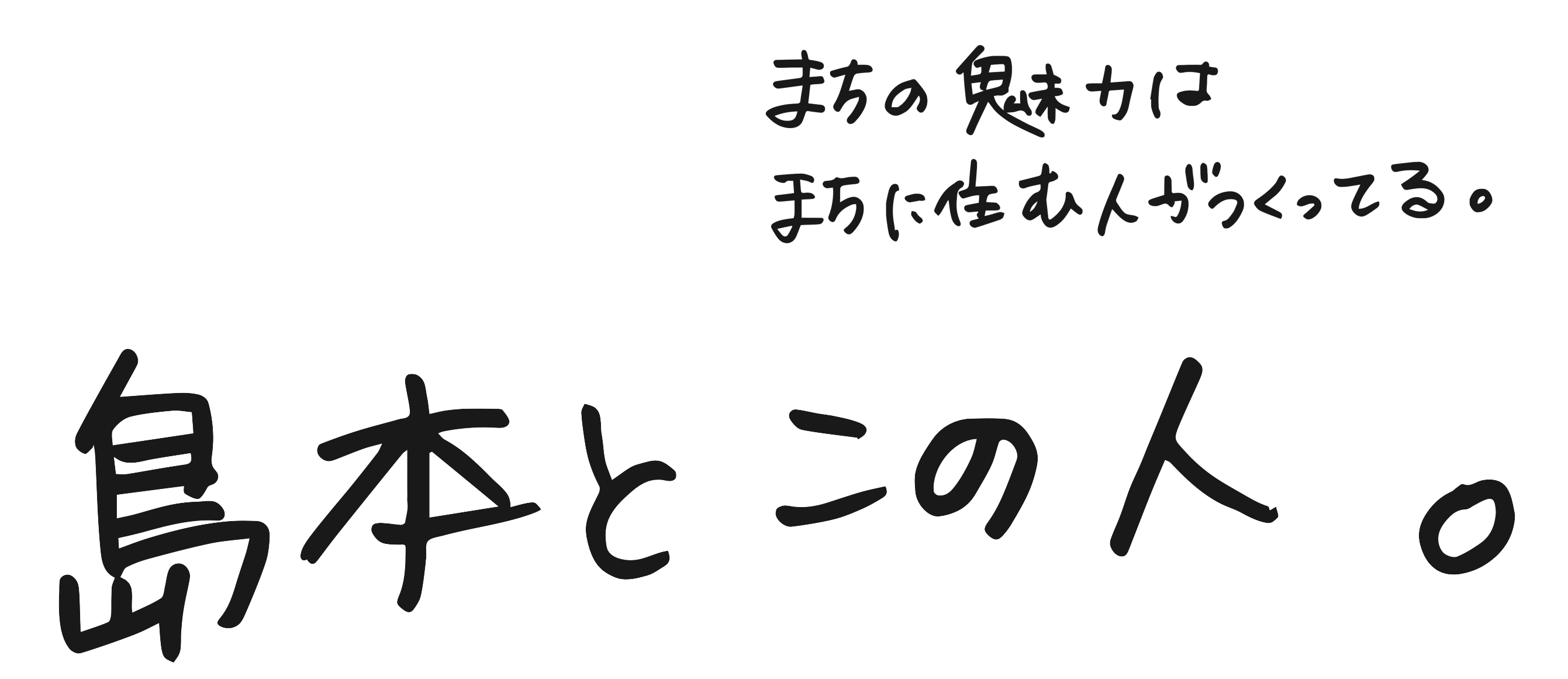

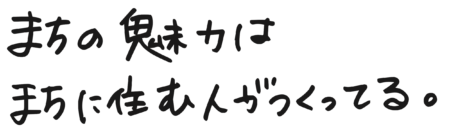
〜今月のこの人〜
狩野 庸さん

悲願の達成
ついにこの日がやってきた――。令和元年(2019)12月8日、ニューヨークのアポロシアターで開催されたダブルダッチの国際大会で、島本ダブルダッチクラブ(SDDC)のチームがオープンパフォーマンス部門第3位という快挙を成し遂げたのである。彼らにとっては待ち望んだ景色であり、悲願だった。
ダブルダッチとは、2人の回し手(ターナー)が2本の長いロープを交互に回し、その中で1~2人のジャンパーが技を交えながら跳ぶ競技である。規定種目・スピード種目のほか、演技の自由度が高いフリースタイル種目などがあり、縄の中でアクロバットな動きやダンスなど、いろいろな要素が詰めこまれている。チームごとにコンセプトを考え、ファッション、音楽など、自由に表現できることがダブルダッチの魅力だ。

ダブルダッチとの出会い

平成18年(2006)、島本町体育協会のスポーツ教室として「ダブルダッチ教室」が開講された。さらに教室の練習だけでは物足らなくなり、平成20年に「島本ダブルダッチクラブ」を立ち上げた。隔週でのスポーツ教室から毎週練習をするクラブへとステップアップをはかったのである。主宰者の狩野庸さんが大学を卒業した直後のことであった。
狩野さんは大学生の時ダブルダッチと出合う。入学式のセレモニーでダブルダッチのステージがあり、衝撃を受けた。「純粋にめちゃくちゃかっこよかった。本当に心奪われるとはあのことだった」と語る。すぐにダブルダッチのサークルに入部した。
固定観念の払拭

チーム運営に当たって留意した点は?との問いに、「とにかく全員がダブルダッチを楽しめる環境を目指しました。その際、クラス分けやレベル分けなどの固定観念をできるだけ払拭しました」と答える。
年齢や学年、性別で人を分けず、お互いに声を掛け合い、教えあう――。全員にとって参画感があり、それぞれ自分に役割があるような空間、またそういった価値観を大切にできる集団にしたかった。今でこそ、ダイバーシティ(多様性)やSDGsなどの概念が注目されているが、それを先取りしていたといっても過言ではない。
「勝利至上主義だけでは、集団として弱くなります。楽しみながら大会に出るチームもあっていい。また、パフォーマンスの内容や音源作成もどんどん本人たちに振るようにしました」と熱く語る。また小学生だった教室生が、そのまま中学・高校・大学に上がっても続け、その子らが小学生を指導するという好循環も生まれた。
このようなチーム作りが奏功したのだろう、兵庫県大会で総合3位入賞するなど、関西で開催される大会で徐々に頭角を現すようになる。しかし、全国大会への予選となると、ミス等でいつも惜しい結果で決勝進出を逃していた。とくに平成28年と平成30年の予選敗退は本当に関係者全員にとって悔しかったという。
「ふだん練習で起こらないミスがなければ、確実に決勝に進めていました。自分たちに打ち克つこと、その準備をさせてやれてなかったことが本当に悔やまれました。本人たちとしてもミスに苦しめられた2年でした。ミスをしないことに囚われる必要はないかもしれないですが、もしあの時ミスしなければ、という思いはどうしても出てしまうものです」
そこで狩野さんは選手たちに、「なぜ大会に出るのか」「なぜこのメンバーでやり抜こうとしているのかなぜこの音楽を使用するのか」、と一つ一つ自分自身で考えさせた。「勝つことそのものを目標にしてしまうと、メッセージ性や作品の質が伴わず、ミス一つで負けてしまったり、そもそも煮詰まっていないことから、ミスを誘発してしまいます。」
これまで紆余曲折があったが、本人たちの力で勝ち取った意義ある勝利であった。それを横で見ていたメンバーも感化されたのだろう、2年連続でJAPAN大会に進出している。先輩たちの頑張りは、次の世代に引き継がれていった。
「これから先、ダブルダッチを島本の1つの文化にしていきたいと思っています」


ダブルダッチは運動が苦手でも縄回しで活躍できる。アクロバットが苦手でもダンス・リズム感でチームに貢献ができる。ダンスが苦手でも足のステップやアクロバットなどでも活躍できる。つまり、その人特有の活躍の仕方があり、全員が主役になれる。
「島本町でダブルダッチやストリートダンスの祭典、または、コンテストを開き、外から人が来て盛り上がりたいですね。さらに種目を問わず、大きなステージを作り、ミックスカルチャーなイベントを作りたい」
島本町という小さくとも豊かなまちが、「ダブルダッチの聖地」となることを夢見て――。



