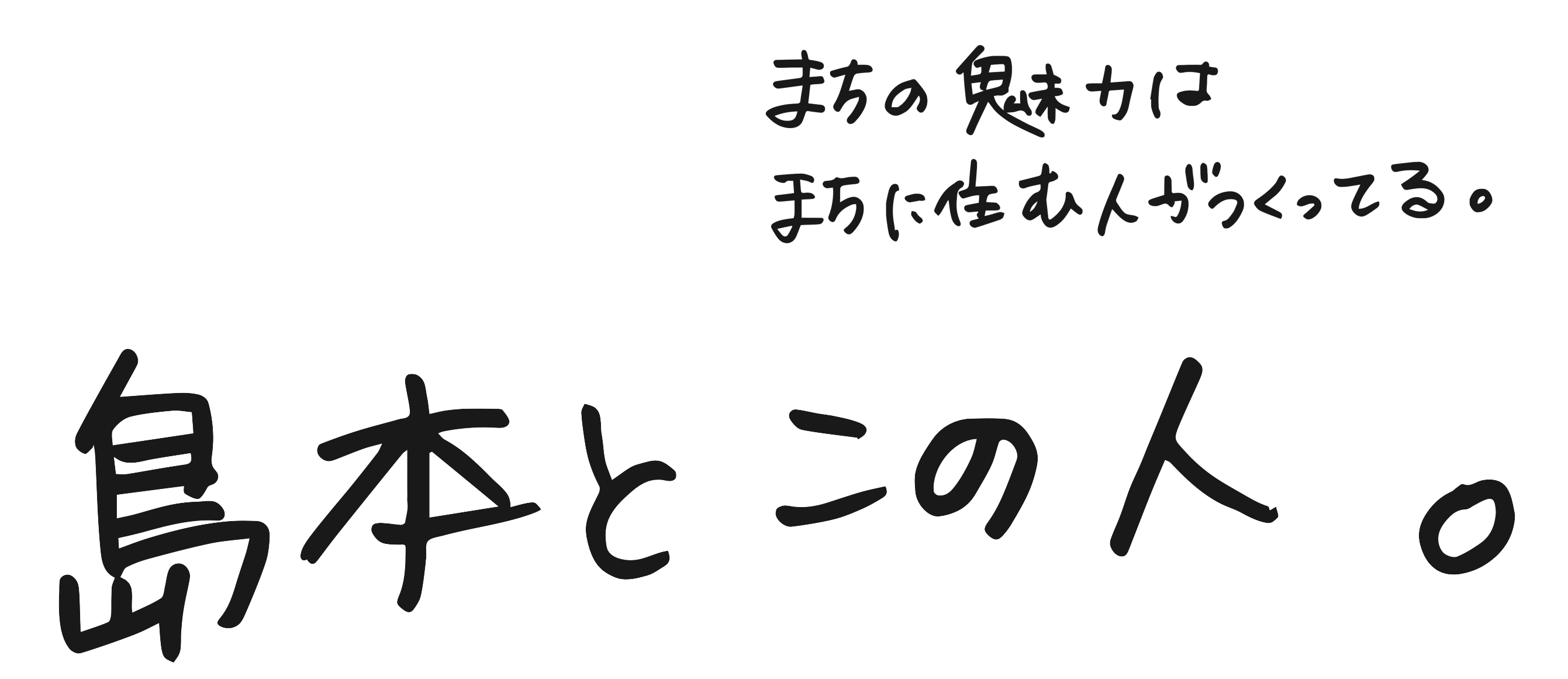

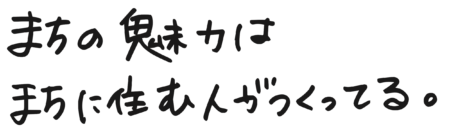
〜今月のこの人〜
関山 利道さん

「新しい景色」を見るために
◆父の突然の死
関山利道九段は、囲碁の解説や講義が非常に上手く定評がある。そのため、地元の囲碁教室はもちろんのこと、所属する関西棋院でも解説することが多い。テレビやラジオへ呼ばれ、大学でも講演を行なった。その縁もあり、5月公開の映画『碁盤斬り』にも出演。冒頭の碁を打つシーンは、関山さんの手である。
「ターニングポイントは父の突然の死でした。持病もなかったのに55歳という若さだったんです。私が19歳の時、いつものように父のマッサージをして、最後に『ありがとう』って言ったのが最期の言葉でした」
すでにプロ棋士になっていた関山さんは、父であり師匠の関山利夫九段が開いていた囲碁教室を手伝って間もないころだった。しかし父の死によって、そこを引き継ぐことになる。タイトルを取るために自らの囲碁の研究に打ちこむだけでなく、教室を開催するという二足のわらじ生活によって、立て板に水のごとく話す名調子の講義は磨かれていった。
「囲碁棋士には主に2つの仕事があります。1つは自身の対局、もう1つは囲碁の普及活動でして、囲碁の楽しさや魅力を伝えることなんです。そういう意味では他のプロに比べ早い段階で普及活動にも取り組めましたね」

碁は幼稚園の時から始めた。小学校に上がると、有段者の元へ習いに行き、深夜1時ごろ帰宅することもあった。小学校5、6年からプロへの道を意識しはじめる。というのも何を隠そう利道さんは、囲碁史上初の親子三代連続九段(九段が最高段位)という、囲碁界のサラブレッドなのである。祖父利一は、初代「本因坊タイトル」を獲ったレジェンドであり、父もNHK杯に出場するなどの一流棋士だった。中学3年の時にプロになり、順調に段位を取得し、平成3年(1991)年には新人賞、平成14年29歳の時についに九段となった。ちなみに九段は全国に100人ほどしかいない。その難関さがうかがい知れよう。
「ふつうはプロ棋士になったときが一番うれしいものなのですが、私の場合は九段を取得した時でしたね。やっと一人前になった気がしました。祖父や父が偉大だったのでプロになるのは当たり前っていう感覚がすごい強かったんです」

◆自分の頭で考える
ここで関山さんの現在を追ってみよう。主に水曜日が対局。対局は朝10時に始まり、終局は夕方、遅いときは夜8時ごろになる。一局終わると体重が1~2キロ減るといわれ、月・火は体力づくりにと、小さい頃から始めたスイミングを今も継続している。
週末の囲碁教室は賑やかである。30名ほどの子どもたちが通い、母の良枝さんや奥様の香さんも囲碁インストラクターとして手伝っている。年上の子が年下の子を教えるなど、さながら寺子屋のようである。
「今のこの一手は何のために打ったのかな」。関山さんはじーっと生徒の反応を待つ。しばらくして「えーっと、この陣地を取るためです」と答えると、「よく分かったね~。そうそれが正解だよ」と誉める。すぐに正解を教えるのではなく、子どもたちにそこに打った意味を考えさせる。「継続は力なり」をモットーに一歩一歩向上させ、その都度生徒たちに「新しい景色を見てもらいたい」という。今までと違った自分になっているからだ。
「囲碁の実力だけでなく学力も伸びる子が不思議と多いんですよ。おそらく集中力はもちろんのことですが、自分の頭で考えて答えを導くというプロセスそのものが鍛えられるからではないかと思うんです」
確かに以前東京大学で囲碁講座が開設され話題を呼んだことがある。年齢の異なる生徒同士での勉強は、昨今話題の北欧諸国の教育方法と相通じる部分もあり、生徒たちの成長ぶりが楽しみである。関山さん念願の島本町からプロ棋士が生まれる日もそう遠くないかもしれない。

◆AIとともに
囲碁の実力といえば、平成28年、囲碁のトッププレイヤーが人工知能(AI)「アルファ碁」に敗れたというニュースが世界中を駆けめぐった。それまでチェス、将棋など人類の知性の象徴とされてきたゲームで次々にAIによる「人間超え」が起きていたが、ボードゲームの王者である囲碁までが陥落することを予想する人はいなかった。
「AIの登場は囲碁界にとって、もう黒船が来航したみたいな衝撃でしたね。そのせいでここ数年で様変わりしたんです。昔は特定の師匠についてその影響を色濃く受けながら学んでいましたが、今の若い子はAIで勉強してすごく活躍しています」
関山さん自身もAIを活用している。まず自分で考えて打ってみる。その後AIの打つ手をみてみる。違った場合AIがなぜそこを打つのかと考えると思考がより深まるという。
「囲碁棋士の中では、ぼくはAIの登場をポジティブにとらえています。師匠からの厳しい指導だけでなく、AIでも研究できるなんて、魅力的な時代に生きているなと」
自分の目標の公式戦通算500勝まであと少し。そのとき関山さん自身も「新しい景色」を見ることだろう。




